記事公開日
建築物省エネ法とは?省エネ法との違いなど現場監督が知っておくべきポイントをわかりやすく解説!
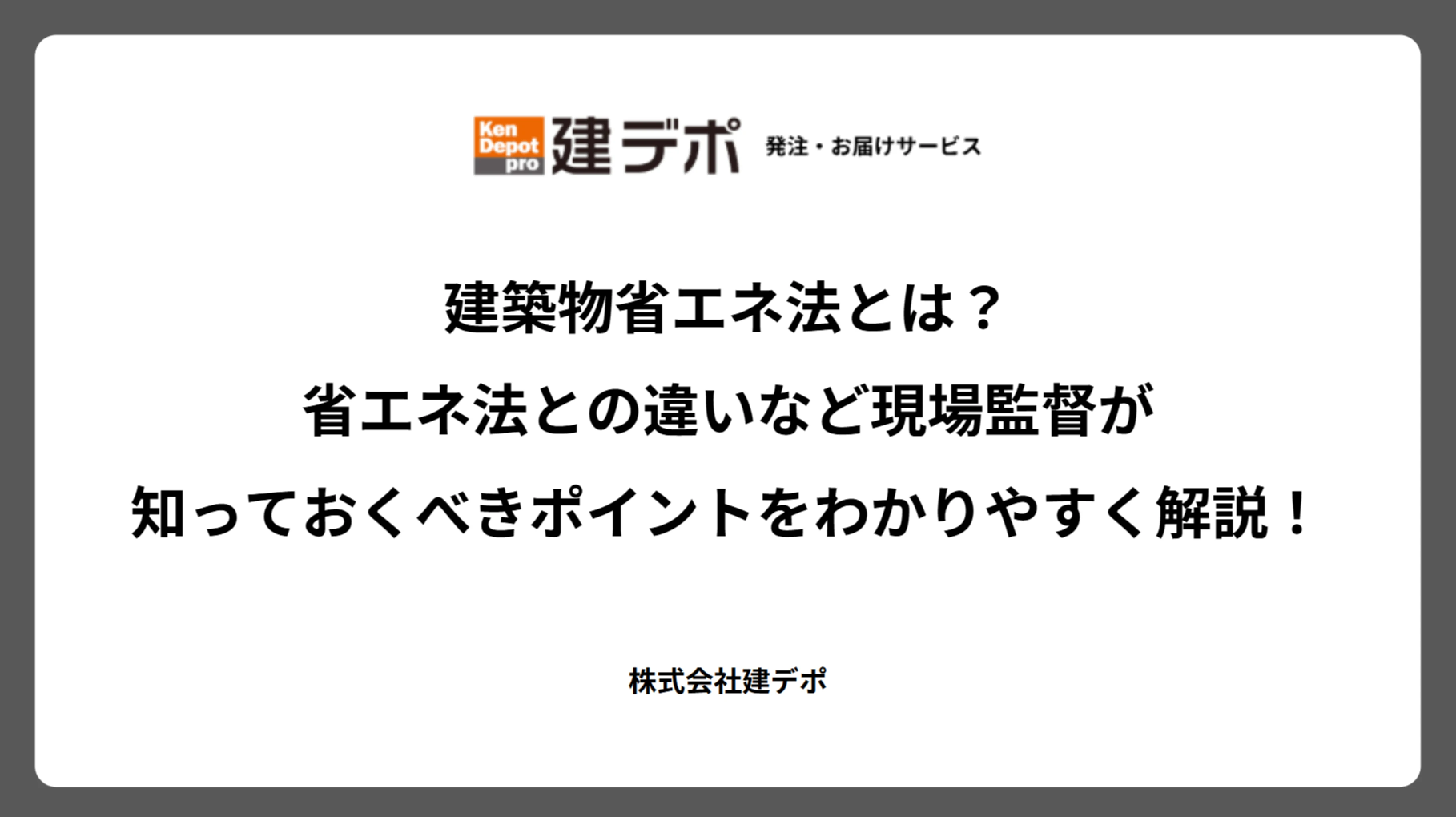
建築物省エネ法の詳細や、従来の「省エネ法」との違いについて、正確に理解できているでしょうか?
特に、建設現場で指揮を執る現場監督の方々にとっては、法令遵守はもちろんのこと、施主からの質問に的確に答えられる知識が不可欠です。
しかし、複雑な法律用語や専門的な内容をすべて把握するのは簡単ではありません。
そこでこの記事では、現場監督の皆様が知っておくべき「建築物省エネ法」の要点を、従来の省エネ法との違いも交えながら、わかりやすく解説いたします。
建築物省エネ法とは?
建築物省エネ法は、正式には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といい、2015年7月に制定され、2017年4月より段階的に施行された法律です。
この法律の主な目的は、建築物の省エネルギー性能を向上させることで、地球温暖化対策やエネルギーの安定供給に貢献することにあります。
具体的には、建築物の新築や増改築、大規模な修繕・模様替えを行う際に、一定の省エネ基準への適合を義務付けたり、省エネ性能の表示を推奨したりすることで、建築物におけるエネルギー消費量を削減し、より環境に配慮した社会の実現を目指しています。
現場監督の皆様にとっては、この法律が定める基準や義務を理解し、現場で適切に対応することが求められます。
この法律は、住宅だけでなくオフィスビルや商業施設といった非住宅建築物も対象とし、建築物の種類や規模に応じて異なる義務が課せられます。
建築物の設計から施工、運用に至るまで、省エネルギーに関する取り組みを促進するための重要な枠組みとなっています。
詳細については、国土交通省の関連情報をご確認ください
建築物省エネ法と省エネ法の違い
「建築物省エネ法」と「省エネ法」は、どちらもエネルギーの効率的な利用を目的とした法律ですが、その対象範囲や目的、そして管轄省庁において明確な違いがあります。
現場監督として、これらの違いを正確に理解することは、適切な法遵守と業務遂行のために不可欠です。
それぞれの法律の対象と目的
まず、それぞれの法律が何を対象とし、どのような目的を持っているのかを理解することが重要です。
省エネ法
省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)は、1979年に制定された日本のエネルギー政策の根幹をなす法律です。
その対象は非常に広範で、工場、事業場、輸送、建築物、機械器具(家電や自動車など)といった幅広い分野におけるエネルギーの使用全般をカバーしています。
この法律の主な目的は、エネルギーの使用の合理化を促進し、国民生活の安定と経済の健全な発展に寄与することであり、地球温暖化対策の一環としても位置づけられています。
建築物省エネ法
一方、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、2015年に制定された比較的新しい法律です。
その名の通り、対象は建築物に特化しており、特に新築や増改築、大規模な修繕・模様替えを行う際の建築物のエネルギー消費性能の向上を目的としています。
この法律は、建築物分野におけるエネルギー消費量の削減と、それによる低炭素社会の実現を目指し、建築物の省エネ性能の向上を通じて、国民の健康で文化的な生活の確保に貢献することを目的としています。
つまり、省エネ法が日本全体の包括的なエネルギー政策を担うのに対し、建築物省エネ法は建築物という特定の分野に焦点を当てた専門的な法律である点が最大の違いです。
管轄省庁と役割の比較
両法律は、それぞれ異なる省庁が主な管轄となり、その役割も異なります。
省エネ法
省エネ法の主な管轄省庁は、経済産業省(資源エネルギー庁)です。
経済産業省は、エネルギー政策全般の企画・立案、工場や事業場、輸送部門などへのエネルギー使用に関する規制や支援策の実施を担っています。
省エネ法に基づく特定事業者への指導や報告徴収なども、同省の役割です。
建築物省エネ法
これに対し、建築物省エネ法の主な管轄省庁は、国土交通省です。
国土交通省は、建築物の設計・施工段階における省エネ基準の適合義務、性能向上計画認定制度、表示制度の運用など、建築物の省エネ性能に関する具体的な規制や誘導策を所管しています。
建築確認申請との連携も、この法律の大きな特徴です。
両省庁はそれぞれの役割を担いつつも、連携して日本の省エネルギー政策全体を推進しています。
現場監督としては、建築物の省エネ性能に関する具体的な義務や手続きについては国土交通省が所管する建築物省エネ法を、それ以外の広範なエネルギー使用に関する規制については経済産業省が所管する省エネ法を意識する必要があります。
建築物省エネ法の対象となる建築物
建築物省エネ法は、建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とした法律であり、その対象となる建築物は、その用途、建築行為の種類、そして規模によって細かく定められています。
現場監督としては、担当するプロジェクトがどの区分に該当し、どのような義務が課されるのかを正確に理解しておくことが不可欠です。
住宅と非住宅の区分
建築物省エネ法では、建築物を大きく「住宅」と「非住宅」に区分し、それぞれに異なる省エネ基準や規制を適用しています。
「住宅」とは、一戸建ての住宅や共同住宅など、人の居住の用に供する建築物を指します。
一方、「非住宅」とは、事務所、店舗、工場、学校、病院など、住宅以外のすべての建築物を指します。
これらの区分は、建築物の利用形態や求められるエネルギー消費性能が異なるため、法律の適用において重要な基準となります。
新築・増改築・大規模修繕・模様替えの区分
建築物省エネ法の対象となる建築行為は、単なる新築にとどまらず、既存建築物に対する特定の改修行為も含まれます。
- 新築…新たに建築物を建設する行為。
- 増改築…既存の建築物に床面積を増やす増築や、既存部分の構造・用途を変更する改築を行う行為。
- 大規模の修繕…建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)の過半を修繕する行為。
- 大規模の模様替え…建築物の主要構造部の過半を模様替えする行為。
これらの行為の区分により、適用される義務の内容や範囲が異なります。特に、増改築や大規模修繕・模様替えの場合、既存部分と増改築部分の扱いなど、複雑な適用関係が生じることがあります。
規模による義務の違い(特定建築物と小規模建築物)
建築物省エネ法では、建築物の規模(床面積)によって課される義務の重さが異なります。
これは、「特定建築物」と「小規模建築物」という区分で明確にされています。
特定建築物における義務
非住宅建築物で床面積が300㎡以上のもの、または共同住宅で床面積が300㎡以上のものが「特定建築物」に該当します。
これらの建築物は、建築物省エネ基準への「適合義務」が課せられます。
これは、建築確認申請時に省エネ基準への適合審査を受ける必要があり、適合しない場合は建築することができません。
この義務は、大規模な建築物の省エネルギー性能を確保し、社会全体のエネルギー消費量削減に貢献することを目的としています。
小規模建築物における義務
一方、床面積が300㎡未満の住宅や、床面積が300㎡未満の非住宅建築物は「小規模建築物」に分類されます。
これらの建築物には、原則として適合義務は課されませんが、建築主への「説明義務」や、一定規模以上の場合は「届出義務」が課せられます。
たとえば、床面積が300㎡未満の住宅の新築・増改築等では、建築士が建築主に対し、省エネ性能について評価・説明する義務があります。
また、一定規模(例:300㎡未満の非住宅で床面積が10㎡超など)の建築物については、工事着手前に所管行政庁への届出が必要となる場合があります。
これらの義務は、小規模な建築物であっても省エネへの意識を高め、自主的な取り組みを促すことを目的としています。
詳細な基準や最新の情報については、国土交通省の関連資料や、各自治体の建築指導課等で確認することが重要です。
現場監督が知るべき建築物省エネ法の主要な義務と制度
建築物省エネ法は、建築物の設計・施工に携わる現場監督にとって、遵守すべき重要な義務と活用できる制度を定めています。
ここでは、実務で特に押さえておくべきポイントを解説します。
適合義務と届出義務
建築物省エネ法における最も基本的な義務は、建築物の規模や用途に応じて課される「適合義務」と「届出義務」です。
現場監督は、自身の担当する建築物がどちらの義務の対象となるかを正確に把握し、適切な手続きと施工管理を行う必要があります。
特定建築物における適合義務
床面積300㎡以上の非住宅建築物、および特定の大規模な増改築や修繕・模様替えを行う非住宅建築物は、建築物省エネ法の「適合義務」の対象となります。
これは、新築時や増改築時に、建築物が省エネ基準に適合していることを確認・検査機関に審査してもらう義務です。
現場監督は、設計図書に示された省エネ性能が実際の工事で確実に実現されるよう、使用材料の確認や施工方法の管理を徹底し、適合審査に備える必要があります。
小規模建築物における届出義務
床面積300㎡未満の住宅および非住宅建築物は、「届出義務」の対象です。
これらの建築物を新築または増改築する際は、工事着手前に、建築物の省エネ計画を所管行政庁に届け出る必要があります。
現場監督は、届け出られた計画に基づき工事を進め、計画に変更が生じた場合は速やかに再届出を行うよう、設計者や建築主と連携することが求められます。
建築確認申請との連携
特定建築物に課される適合義務は、建築確認申請と一体となって審査が行われます。
つまり、建築確認済証の交付を受けるためには、省エネ基準への適合が必須となります。
現場監督は、省エネ適合性判定の結果が確認済証の交付に影響することを理解し、設計段階からの連携を密にし、施工段階での不適合が発生しないよう注意を払う必要があります。
工事完了後の完了検査でも、省エネ基準への適合が確認されます。
性能向上計画認定と容積率特例
建築物省エネ法には、義務とは別に、より高い省エネ性能を目指す建築物に対するインセンティブとして「性能向上計画認定」という制度が設けられています。
誘導基準の解説
性能向上計画認定を受けるためには、建築物が「誘導基準」と呼ばれる、省エネ基準よりも高い水準の省エネ性能を満たす必要があります。
誘導基準は、一次エネルギー消費量や外皮性能などにおいて、一般的な省エネ基準を上回る目標を設定しており、より優れた環境性能を持つ建築物の普及を促進することを目的としています。
認定を受けるメリット
性能向上計画認定を受けた建築物には、主に以下のメリットがあります。
現場監督は、これらのメリットを理解し、設計者と協力して認定取得に向けた施工品質の確保に努めることが重要です。
容積率特例
省エネ性能向上のために設ける設備(蓄電池、再生可能エネルギー設備など)の床面積が、一定の範囲内で容積率の計算から除外されます(最大10%)。
これにより、よりゆとりのある設計や設備導入が可能になります。
税制優遇
所得税、法人税、不動産取得税、固定資産税などの優遇措置が受けられる場合があります。
詳細については、国土交通省の関連情報を参照してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」は、建築物の省エネ性能が一定の基準を満たす場合に、所管行政庁から認定を受けることができる制度です。
この認定は、建築物の資産価値向上や、環境に配慮した建築物としての評価向上に繋がります。
BELS(ベルス)とZEH(ゼッチ)との関連性
建築物エネルギー消費性能向上計画認定は、BELS(ベルス:Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)やZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)といった、建築物の省エネ性能評価や目標達成と深く関連しています。
BELSは、建築物の省エネ性能を第三者が評価し、星の数などで表示する制度であり、ZEHは年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指す住宅です。
現場監督は、これらの高い省エネ目標が設定された建築物の施工において、断熱性能の確保、高効率設備の導入、気密性の向上など、設計通りの品質を確保する重要な役割を担います。
表示制度と情報提供努力義務
建築物省エネ法では、建築物の省エネ性能に関する情報提供を促すための制度も設けられています。
建築物の省エネ性能表示
建築物の所有者は、その建築物の省エネ性能について、第三者機関による評価結果(BELSなど)を建築物の広告や入居者募集時に表示することができます。
これにより、建築物の省エネ性能が「見える化」され、消費者が省エネ性能の高い建築物を選びやすくなります。
建築主への説明義務
建築士は、新築や増改築の設計を行う際に、建築主に対し、設計する建築物が省エネ基準に適合するかどうか、また省エネ性能を向上させるための措置について説明する義務があります。
現場監督は、この説明内容を理解し、設計者(建築士)と連携しながら、建築主の省エネへの意識や要望を施工に反映させる役割を担います。
建築物省エネ法遵守のメリットと違反時のリスク
建築物省エネ法を遵守することは、社会的な責任だけでなく、建築主や施工者にとって多くのメリットをもたらします。
一方で、違反した場合には重大なリスクが伴います。
遵守によるメリット
建築物省エネ法の基準を遵守し、さらに高い省エネ性能を追求することは、単なる義務の履行に留まらず、建築物の価値を高め、長期的な利益をもたらす多くのメリットがあります。
建築物の資産価値向上と光熱費削減
高い省エネ性能を持つ建築物は、居住者や利用者にとっての光熱費負担を大幅に軽減します。
これにより、入居者や購入希望者からの需要が高まり、賃貸物件であれば空室リスクの低減、売買物件であれば売却価格の向上につながり、結果として建築物全体の資産価値が向上します。
また、企業のESG投資やSDGsへの取り組みが重視される現代において、環境性能の高い建築物は企業イメージの向上にも貢献します。
補助金や優遇税制の活用
建築物省エネ法に基づく認定制度(性能向上計画認定など)を活用し、誘導基準に適合する建築物を建築した場合、国や地方自治体から提供される様々な補助金や税制優遇措置の対象となる可能性があります。
たとえば、不動産取得税や固定資産税の減額、住宅ローン金利の優遇などが挙げられます。
これらの制度を積極的に活用することで、初期投資の負担を軽減し、経済的なメリットを享受できます。
具体的な制度については、国土交通省や地方公共団体のWebサイトで確認できます。
違反した場合のリスクと罰則
建築物省エネ法は、建築物の省エネ性能確保を目的とした重要な法律であり、その義務に違反した場合には、事業の継続性や信頼性に大きな影響を及ぼすリスクと罰則が科せられます。
是正命令や罰金
特定建築物における適合義務や、届出義務を怠るなど、建築物省エネ法に違反した場合、所管行政庁から是正命令が出されます。
この命令に従わない場合、建築主や設計者、施工者に対して最大300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、建築士法に基づく懲戒処分や、建設業法に基づく監督処分に発展するケースも考えられ、業務停止や登録取り消しといった重大な事態に至る可能性も否定できません。
工事の中止命令
特定建築物において、建築確認申請時に省エネ基準への適合が確認されなかった場合や、工事中に適合しない事実が発覚した場合、所管行政庁から工事の中止命令が出されることがあります。
工事が中断すれば、工期の遅延による追加コストの発生、資材や労力の無駄、そして何よりも施主や関係者からの信頼失墜という深刻な影響が生じます。
場合によっては、建築確認の取り消しや、建築物の使用制限が課される可能性もあり、事業運営に甚大な損害を与えるリスクを伴います。
まとめ
建築物省エネ法は、現場監督にとって重要な法律です。
本記事で解説したように、省エネ法との違い、対象建築物の区分、適合義務、届出義務、性能向上計画認定といった制度を正確に理解することが鍵です。
この法律を遵守することは、建築物の資産価値向上や補助金活用などのメリットがある一方、違反時には是正命令や罰則、工事中止といった重大なリスクを伴います。
現場監督は常に最新情報を把握し、適切な施工管理を徹底し、環境配慮と建築主の信頼に応えましょう。